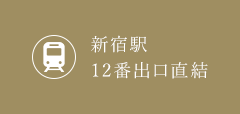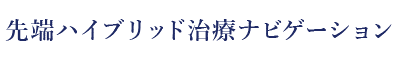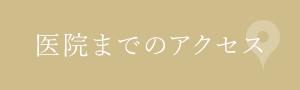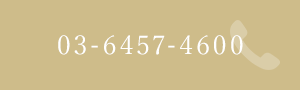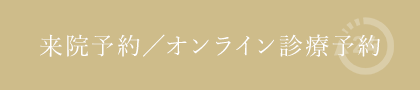ピロリ菌感染とは?
 実は、ピロリ菌に感染しただけではほとんど症状が現れません。 しかし、長期にわたって感染が続くことで、慢性胃炎や胃潰瘍・十二指腸潰瘍を引き起こすと、それら疾患の症状が現れます。 なお、ピロリ菌に感染すると口臭が強くなることがあります。これは、ピロリ菌がアンモニアなどの有害な物質を出すことによって起こります。
実は、ピロリ菌に感染しただけではほとんど症状が現れません。 しかし、長期にわたって感染が続くことで、慢性胃炎や胃潰瘍・十二指腸潰瘍を引き起こすと、それら疾患の症状が現れます。 なお、ピロリ菌に感染すると口臭が強くなることがあります。これは、ピロリ菌がアンモニアなどの有害な物質を出すことによって起こります。
- 胃やみぞおちの痛み
- 胃のむかつき
- 胃が重い感じ
- 胸やけ、胃の不快感
- 吐き気、嘔吐
- 腹部の張り、膨満感
- 食欲不振
- 黒い便(タール便)
- 吐血
- 口臭
ピロリ菌に感染する原因(感染経路)
ピロリ菌は、経口感染します。ただ、5歳くらいまでに感染するものであり、それ以上の年齢になってから感染するということはないと考えられています。
ピロリ菌は遺伝する?
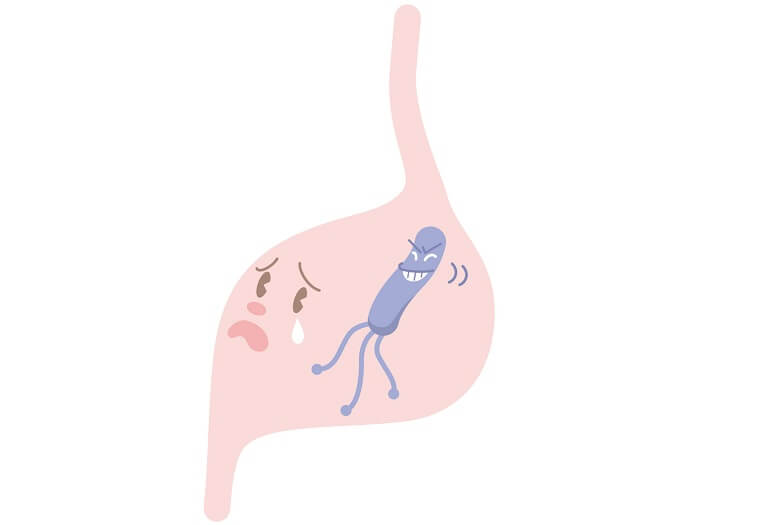 ピロリ菌が親から子へと遺伝することはありません。
ピロリ菌が親から子へと遺伝することはありません。
しかし、感染している・感染しているかもしれない親から子への食べ物の口移し、親子の唇同士のキスなどは感染リスクの高い行為と言えます。つまり遺伝性はないものの、親から子へとピロリ菌を受け継いでしまう可能性は十分にある、ということです。
なお、かつては井戸水を介して感染していたようですが、井戸を使う家庭がほとんどない現代においては、そういった症例はほとんどないと言えます。
ピロリ菌はキス・性行為でうつる?
ピロリ菌は、感染している人から5歳くらいまでの子どもへと感染するものです。
そのため、親子の唇同士のキスでうつるということは十分に考えられます。一方で大人同士のキスでは、感染することはありません。
また性行為についても同様に、感染の心配はありません。
ピロリ菌感染は胃がんリスクが高まります
 ピロリ菌に感染したまま放置していることは、慢性胃炎・萎縮性胃炎の原因となります。そして萎縮性胃炎の一部は、胃がんへと進行します。
ピロリ菌に感染したまま放置していることは、慢性胃炎・萎縮性胃炎の原因となります。そして萎縮性胃炎の一部は、胃がんへと進行します。
このように、ピロリ菌感染の放置は、胃がんのリスクを高めてしまうことにつながります。
ピロリ菌の検査を受けたことのない方は、早めに検査を、そして必要に応じて除菌治療を受けることをおすすめします。
ピロリ菌感染の検査
尿素呼気試験
13C-尿素を含む検査薬の服用前後に、吐息を採取し成分を分析します。
ピロリ菌が出すウレアーゼが、尿素を二酸化炭素とアンモニアへと分解する性質を持つことを利用した、非常に精度の高い検査です。
※当院では対応しておりません。
便中抗原検査
便中のピロリ菌に対する抗原の有無を調べます。
抗原がピロリ菌に対して特異的な反応を示すことを利用した検査です。
血中・尿中抗体検査
血液または尿の中の、ピロリ菌感染によって産生される抗体の有無を調べます。
内視鏡検査
内視鏡検査の際、胃粘膜を観察して判定します。
発赤、白色粘液の付着、ひだの肥厚などが認められた場合に、感染を疑います。
病理組織学的検査
内視鏡検査で採取した組織を染色し、顕微鏡で観察してピロリ菌の有無を判定します。
迅速ウレアーゼ試験
内視鏡検査で採取した組織を検査試薬内に入れ、pH指示薬の色調の変化で判定します。
ピロリ菌の産生するウレアーゼが、アンモニア(アルカリ性)が生じさせる性質を利用した検査です。
培養法
内視鏡検査で採取した組織から菌を分離し培養させることで、ピロリ菌の有無を判定する検査です。
ピロリ菌の治療
ピロリ菌の治療では、ピロリ菌の除菌を行います。3つの薬を毎日2回、連続して7日間服用します。
一次除菌が失敗に終わった場合には、薬の種類を替えて二次除菌へと進みます。
ピロリ菌除菌が成功する確率はどのくらい?
一次除菌の成功率は、90%ほどです。
二次除菌を含めると成功率はさらに高くなり99%に達します。
除菌に失敗する場合ってどんなとき?
除菌の失敗例のうちほとんどを占めるのが、指示通りの服用ができなかった(忘れてしまった)ケースです。
除菌に失敗すると、ピロリ菌が耐性を持ってしまうことがあるため、十分な注意が必要です。
除菌の副作用はある?
軽い下痢、味覚異常、発疹などいくつかの副作用が報告されています。
下痢や味覚異常については、症状の程度によりますが、患者様と相談した上で除菌を継続することが多くなります。
一方で発疹、血便・粘液便、発熱・腹痛を伴う下痢が現れた場合には、直ちに服用を中止し、ご連絡ください。